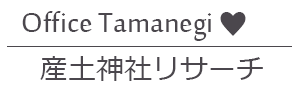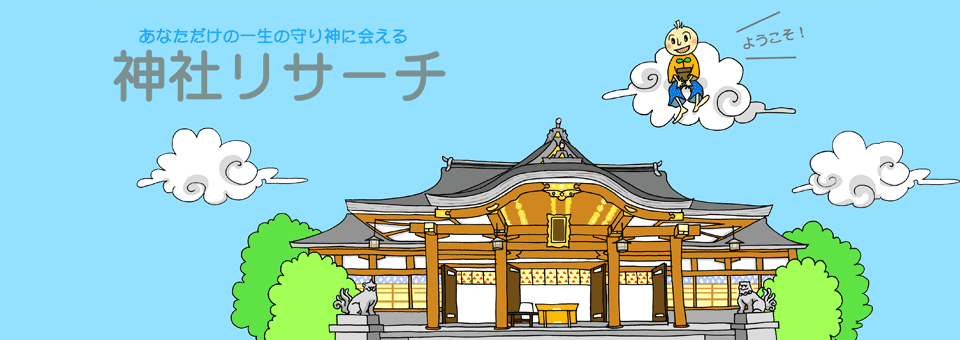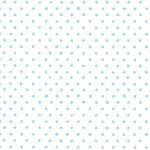3)祓い・罪・穢れ(ケガレ)とは?
のつづきです。
神社で行われる「祓い」とはなんでしょう?
一般的には、悪いものをサっと「払う」
というイメージがあるかと思いますが、
よく考えてみると、それでは悪いものが
「どこかへ移動しただけ」で、
何の解決にもなっていません。
「祓い」というのは、
もっと上をいくすごい神事です。
悪いものがどこかへ去っていくというより、
それそのものを、いいものに戻してしまう
というイメージです。
神様のすばらしい力が注ぎこまれることで、
「マイナス」だったのものが「ゼロ」へ、
そしてさらに「プラス」へと
すっかり変換されてしまうことをいうのです。
包み隠されてしまっていた
イキイキとした命がよみがってくる、
それが「祓い」なのです。
「罪(つみ)」は
人間の良くない行為によって起こりますが、
「犯罪」という意味ではなく、
神様が生んでくださった素晴らしい本来の姿を
包み隠してしまうものを
「つみ(包む身)」といいます。
では「穢れ」はどうでしょう?
「けがれ」と聞くと、一般的には
「汚れ」という漢字をイメージしますよね。
「清浄」とは反対の「汚れて悪しき状態」
だと想像がつくと思います。
神道では「穢れ」と書き、
物理的な汚れはもちろんですが、
目に見えないエネルギーの汚れをも意味し、
神様からもらった本来の
すばらしい姿でなくなってしまう、
と考えられました。
「穢れ」は自然発生してしまう、
ある意味仕方がないものですが、
これらが溜まっていくと
世の中や人間に「災い」を
引き寄せやすくなってしまうので、
それを防ぐために神道では
「禊(みそぎ)」や「祓い」を大切にしています。
また、「穢れ」は
「=気が枯れる」とも考えられており、
「人間の霊力が、枯れて弱ること」をいいます。
ネガティブな「気」や「エネルギー」に
触れれば触れるほど、
元気(神様の気)がどんどん無くなっていってしまいます。
これは決して人や環境のせいだけではなく、
自分自身の思いグセが悪かったり、
悪口を言うことでも気が枯れてしまいます。
比叡山で千日回峰行を達成された
阿闍梨の方もおっしゃっていましたが、
この世の暮らしや人づきあいは、
あの辛い千日回峰行よりも大変だそうです。
そんな暮らしを営む私たちに
「罪・ケガレ」が溜まってしまうのは仕方がないことです。
だから年に2回の「大祓」は
貴重なチャンスといえるでしょう。
その際に、
神様の素晴らしい力をいただくためには、
なるべく「気」が充実した状態に近づけて神社へ行きましょう。
その方がいいエネルギーを受け取ることが出来るからです。
それには、自分ができる範囲で
心身を清めて神社に向かいます。
(清潔にする、きちんと身支度を整える、
自宅の掃除をしてスペースを作っておく)
そうすればあとは神様が、
人間ができないエリアの大掃除をして、
たっぷりとプラスのエネルギーを注いでくださいます。
リセットされ、生まれ変わった気持ちで
新しい日々を過ごしていけるでしょう。
年に2回の「大祓」は外すにはあまりにもったいない、大切な日本の神事です。
次回は「夏越の大祓」(全体の流れ)についてご紹介します。
<参考>
神道辞典
神社神道の常識
大祓 知恵のことば
「大祓」解説シリーズ:まとめ
1) 誰でも生まれ変われる・年に2度の「大祓(おおはらえ)」とは?
2)「祓い」の由来は日本の神話から
3) 祓い・罪・穢れ(ケガレ)とは?
4)「夏越の大祓」とは?(全体の流れについて)
5)「夏越の大祓」とは?(形代の作法について)
6)「夏越の大祓」とは?(茅の輪のくぐり方)
7)「夏越の大祓」当日に参加できない場合
8)「大祓」解説シリーズ:まとめ
9)「茅の輪」は、引き抜いちゃダメなの。